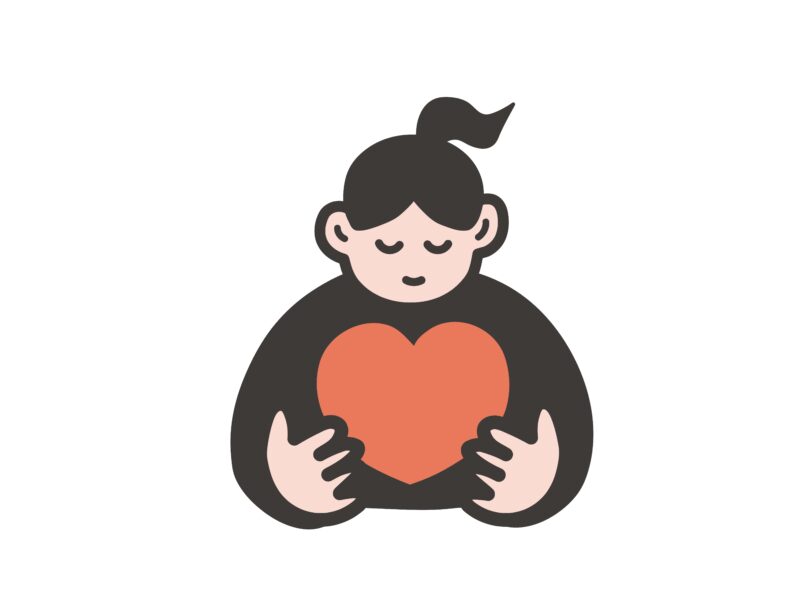
日々、私たちが感じる喜びや悲しみ、怒りや愛といった感情は、すべて心の働きによるものです。ですが、心とは一体何なのでしょうか。古くはスピリチュアルな存在として見なされていた心ですが、現代の心理学や脳科学では、心は脳の働きによって生み出されるものだとされています。
あなたは最近、気持ちの浮き沈みが激しくなったり、感情のコントロールが難しくなったり、無気力に陥ったりしたことがありませんか。もし思い当たる節があるなら、脳の状態が影響している可能性があります。
この記事では、心の正体と不調のサイン、心を健やかに保つ方法を詳しく解説します。心の健康を大切にしたい方はもちろん、毎日をもっと快適に過ごしたい方も、ぜひ最後まで読んでみてください。
心とは?
心とは、感情や思考、意志といった精神的な働きを生み出す源のこと。古くは魂や霊体に似た神秘的な存在として捉えられてきましたが、現代の心理学や医学、脳科学では、脳の働きによるものだと考えられています。
例えば、あなたは動物や子供を見て温かい気持ちになったことはありませんか?
それは、五感を通じて動物や子供といった刺激が脳に伝わり、オキシトシンという脳内物質が分泌されたせい。オキシトシンは愛情や愛着に関係し、心を落ち着かせたり、「愛おしい」という感情を生み出したりします。
また、怒りや喜びなどの感情は、ドーパミンやセロトニン、ノルアドレナリンといった脳内物質の働きによって引き起こされます。つまり、私たちの心の動きは、脳内の化学反応によって生まれていると考えるのがベターです。
心をスピリチュアルなものと考えている人もいるかもしれません。しかし、そのような捉え方をすると、「心はスピリチュアルなものだから、自分にはどうにもできない」と感じてしまうことがあります。
しかし、心は脳の働きによって生み出されるもの。そして、脳は肉体の一部です。
みなさんもご存知のように、肉体は、食事や睡眠、運動などの生活習慣によってその働きを整えることができます。心の正体が脳ということは、心の状態もまた、生活習慣を改善することで程度整えることができるということです。
心の不調とは?
心の正体が脳の働きであるということは、脳の状態が悪化すると、心の状態も悪くなるということです。例えば、十分な睡眠をとれなかったり、何週間も休まずに働き続けたり、ストレスの多い環境に身を置いていたりすると、脳に疲労が蓄積されます。その結果、気持ちが落ち込んだり、塞ぎ込んだり、些細なことでイライラしたりするように。さらに、その状態を放置してしまうと、最終的には『心が病んだ』と呼ばれるような深刻な状態に陥ることもあります。
ですが、脳や心は私たちの目に見えません。肉体に切り傷やあざができたら、パッと見ただけで分かりますよね。しかし、脳や心は目に見えないため、不調を見過ごしてしまうことが多くあります。そこで、次の項目では、みなさんが心のSOSに気づけるよう、代表的な心の不調を5つ紹介します。
気持ちが落ち込む
脳に疲労が蓄積すると、脳の状態が悪くなり、セロトニンと呼ばれる脳内物質の分泌が低下します。セロトニンとは、気持ちを落ち着かせたり、安心感を生み出したりする重要な物質。セロトニンが低下すると、気持ちが落ち込んだり、不安感が強くなったり、憂うつな状態が続いたりします。もし最近、「気分が落ち込む」「なんだか不安だ」と感じることが増えたなら、心がSOSを発している可能性が。
イライラしやすくなる
セロトニンの減少が引き起こすのは、気持ちの落ち込みや不安だけではありません。怒りのコントロール不全もその一つです。些細なことにイライラしたり、周囲の人に当たってしまったりするなら、心がSOSを発しているのだと考えてください。特に、普段は温厚な人が急に怒りっぽくなったという場合は要注意です。また、もともと怒りっぽい性格だと思っている人も、慢性的な脳疲労が原因となっている可能性があります。
人に会いたくなくなる
人に会うことが億劫に感じられることも、心の不調の一種です。友人との予定をキャンセルしたくなったり、スマートフォンの通知が鳴るたびにため息をついていたりするなら、要注意。脳に疲労が溜まり、心の余裕がなくなっているのかもしれません。特に、普段社交的な人が交流を避けるようになったら、心が深刻な状態に陥っている可能性があります。
何もやる気が起きない
仕事に対する意欲が湧かなかったり、家事を始めるのに時間がかかったりすることはありませんか?思い当たる節があるなら、脳疲労からくる心の不調の疑ったほうが良いかもしれません。また、仕事や家事に対する無気力だけでなく、趣味を楽しむ気力が湧かなくなるのも要注意。心が限界に近づいているサインだと考えてください。
わけもなく涙が出る
直接的な原因はないのに涙が出てびっくりしたことはありませんか。それは、心が限界に達しようとしているサイン。特に、泣いた後に気持ちが明るくなったり、スッキリしたりするわけでもなく、ネガティブな感情が持続するなら要注意です。この場合、すでに心が限界に達している可能性もあります。
これらの内容に思い当たる節がある人は、後述する対処法を試してみてください。ですが、その前に、心の健康状態をチェックできる診断テストを受けてみてください。診断を受けることで自分の心の状態を把握できるだけでなく、今のあなたに合った対処法が分かりますよ。
【診断】あなたの心の健康状態をチェック!
以下のチェックリストの中から、「今の自分に当てはまる」と感じた項目にチェックを入れてください。
□ 夜眠るまでに時間がかかる
□ 食欲の低下または過食の傾向がある
□ ネガティブなことばかり考えてしまう
□ 些細なことで怒りやすくなったと感じる
□ 以前は興味があったことに興味が持てなくなった
□ 喜ばしいことがあっても嬉しいと思えない
□ やらなければいけないことを後回しにしてしまう
□ 人と関わることが面倒に感じる
□ 思考力や記憶力が落ちたと感じる
0〜3個当てはまった人:健康な心を保てている状態
あなたは、健康な心を保つことができているようです。
ただし、誰でも脳疲労が溜まれば心の状態は悪化します。日頃から生活習慣に気をつけて、心の健康予防を意識すると良いでしょう。
4〜6個当てはまった人:やや心が疲れている状態
あなたは、やや心が疲れているようです。
休息を必要としている状態なので、できる限り早くに休憩をとったり、休日を設けたりしましょう。また、気分転換になるような趣味を楽しんだり、外出したりするのも良いです。
7〜10個当てはまった人:心が限界に達している状態
あなたは、心が限界に達しようとしているようです。
まずはしっかりと心を休ませましょう。また、可能であれば心療内科を受診したり、心理師(心理士)やカウンセラーなどの専門家に相談すると良いでしょう。
心の健康を保つ方法
それでは、次の項目からはチェックリストで当てはまった項目の数からあなたに合った心のケア方法を4つずつご紹介します。心の健康を保って楽しい毎日を送りたいと考えているなら、ぜひ参考にしてくださいね。
0〜3個当てはまった人:心の不調を予防しよう!
0〜3個の項目に当てはまったあなたは、心の健康を保つことができているようです。ただし、健康だからといって頑張り過ぎたり、無茶をしたりするのは良くありません。今健康な心を維持できていたとしても、脳に疲れが溜まると、誰でも心のバランスを崩すものです。日頃から心の健康に気を配り、心の不調を未然に防ぐようにしましょう。
まずは、以下の3つの方法の中から自分に合いそうなものを1つ選んで試してみてください。実践していく中でもしできることが増やせそうなら、2つ、3つ……と増やしていってくださいね。
心の不調を予防する方法①規則正しい生活をする
心の健康を保つ鍵は、ズバリ心に良い影響を与える脳内物質。中でも、セロトニンの分泌を増やすことができれば、心の健康を維持しやすくなります。セロトニンは、日光を浴びることで分泌が促されます。そのため、昼夜逆転した生活や午後に起床する習慣、カーテンを閉め切った部屋に閉じこもるのは良くありません。規則正しい生活を心がけ、朝起きて夜寝るというリズムを守ることが重要です。
まずは、早寝早起きを心がけてみてください。早寝早起きといっても、午前3時や5時に起きる必要はありません。日の出とともに目覚めるのが理想的です。夏なら6時〜6時半、冬は7時〜7時半に目覚ましをセットすると良いでしょう。また、起床後1時間以内に朝食を摂ると、体内時計がリセットされ、生活リズムが整いやすくなります。
就寝時間は、起床時間を基準に逆算して決めましょう。7時間半以上の良質な睡眠を確保できれば、脳疲労は解消されます。つまり、朝6時半に起きるなら22時30分までには眠り、朝7時半に起きる場合は23時30分までに寝るようにしましょう。月に数回の夜更かしなら大きな問題にはなりませんが、毎日夜更かしを繰り返すのは避けましょう。
心の不調を予防する方法②1日15分以上運動をする
運動は、体だけでなく心にも良い影響を与えます。運動をすると、脳内でセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンといった脳内物質が増加。セロトニンはストレスの軽減やリラックスに効果があり、ドーパミンとノルアドレナリンにはモチベーションを高める働きがあります。これらの分泌が活発になるとことで、心の健康を維持しやすくなるのです。
特に、起床から1時間以内に20分間の散歩やジョギング、ウォーキングを行うと、セロトニンの活性化がさらに進みます。ちなみに、秋から冬にかけては太陽光が弱まり、セロトニンの分泌量が低下。秋冬になると心の調子が悪くなるという方は、9月頃から散歩やジョギング、ウォーキングに取り組むと良いでしょう。
野外で運動するのが難しい場合は、室内で足踏みやスクワットを行うのも効果的です。もちろん、ジムに通って有酸素運動をするのもおすすめ。自分に合った運動方法を選んで、無理なく続けられるようにすると良いでしょう。
心の不調を予防する方法③ストレスを真正面から受け止めない
規則的な生活を心がけ、日光を浴び、適切な量の運動をしていても、強いストレスが原因で心の調子が崩れることがあります。ストレスとは、外部から刺激に対する心理的な反応のこと。人間関係や仕事、育児のストレスで心のバランスが崩れてしまう場合は、ストレスとの向き合い方を見直すことが大切です。
よく『心が強い』『メンタルが弱い』といった表現を耳にしますが、心理学的には、心の強さに個人差はないと考えられています。ストレスで心が乱れる原因は、ストレスの多い環境にいること、ストレスを真正面から受け止る傾向があること、心の支えとなる環境や人間関係が不足しているの3つです。これらが重なれば、誰だって心の状態を悪くしてしまうものなのです。
特に、ストレスを真正面から受け止める傾向がある人は、一つのストレスから受ける心理的なダメージが大きくなりがちです。例えば、上司にミスを叱責されたとき、自分を責めたり、何時間も落ち込んだりして、過剰に反省してはいませんか。しかし、心の健康を保つためには、あまり深刻に受け止め過ぎないことが大切です。「次から気をつけよう」「その言い方は酷いでしょ」くらいに捉え、ストレスを『真に受けない』工夫をすると良いでしょう。
4〜6個&7〜10個当てはまった人:心の健康を回復させよう!
4〜6個または7〜10個の項目に当てはまった人は、心の健康が損なわれている恐れがあります。早急に休息をとり、心に癒しを与えるよう心がけてください。もし、まだ充分に休んでいなかったり、どのように休息をとるべきか分からない場合は、以下の3つの中から1つ選び、実践してみてください。
それでも心の回復が感じられない場合は、専門医や専門家に相談することを強くお勧めします。心の健康を取り戻すための大きな一歩となるでしょう。
心の健康を回復させる方法①質の高い睡眠をとる
脳の疲労を回復するうえで、最も大切なのが睡眠です。心理学や脳科学の観点からも、7時間半以上の質の良い睡眠をとることで、脳の疲れはリセットされるといわれています。「最近、気分が沈みがち」「理由もなく涙が出るほど疲れている」というときは、とにかくしっかりと眠ることが最優先です。夜は22時〜23時の間に就寝し、7時間以上の睡眠を確保しましょう。
ただし、慢性的な寝不足が続いている場合は、7時間半の睡眠では回復しきれないことも。目覚ましが鳴っても起きられなかったり、二度寝したくなったりするなら、脳に疲労が蓄積しているサインです。無理に起きようとせず、充分な睡眠をとるようにしましょう。また、人によっては9時間以上の睡眠が必要なこともあります。朝にスッキリ目覚められるだけの睡眠時間を確保することが大切です。
質の高い睡眠をとるためには、室温を22度前後に保つと良いでしょう。暑すぎたり寒すぎたりすると、夜中に目が覚めたり眠りが浅くなったりするため、快適な温度を維持することが重要です。なかなか寝付けない場合は、寝る90分前までに15分以上の入浴をすると良いでしょう。湯温は39〜40度が理想的です。
心の健康を回復させる方法②何もしない時間を作る
睡眠の次に大切なのが、休息です。何もしない時間を意識的に作り、脳の疲労を解消しましょう。ベッドで横になったり、窓辺でボーッとしたり、ソファでくつろいだりするのがおすすめです。このとき、スマートフォンやタブレット、パソコン、テレビといった電子機器の使用は控えましょう。電子機器の画面から発せられるブルーライトは脳を覚醒させるうえに、インターネットやテレビには興奮や不安を引き起こすコンテンツが多く含まれています。せっかく休む時間を作っても、電子機器を使っていると脳や心の休憩にはなりません。
脳疲労を解消して心の健康を回復させるためには、電子機器を使わない時間を意識的に設けることが大切です。とはいえ、現代人は電子機器に依存していることがほとんど。いきなり丸一日電子機器を使わずに過ごすのは難しいでしょう。デジタルデトックスに慣れるためにも、まずは1時間から試してみるのが良いでしょう。
もし、何もせずに過ごすことが難しいと感じる場合は、家事や掃除をしたり、電子機器を家に置いたまま近所を散歩したりすることから始めてみてください。こうした習慣に慣れていくことで、少しずつ何もしない時間を作りやすくなっていきますよ。
心の健康を回復させる方法③ひとりの時間を確保する
人間関係でストレスを感じることが多い場合や、家族と同居していたり、子育てで忙しい日々を送っていたりする場合は、意識的にひとりの時間を確保することが大切です。脳疲労を解消するためには、脳に不要な刺激を与えないことが大切。ですが、人と関わるとどうしても刺激を受けてしまいます。脳を休めるためにも、ひとりの時間を意識的に作るようにしましょう。
キャンセルできる予定があるなら、思い切って取りやめるのも一つの方法です。多少落ち込んでいるときなら、気心の知れた仲間と会うことで気分が晴れるかもしれません。ですが、精神的に参っているときは、人と関わること自体が負担になります。思い切って予定をキャンセルして、その時間をひとりで過ごすことで、心身をしっかりと休ませましょう。
もし余裕があるなら、趣味に没頭するのも良いでしょう。同居人がいて家でひとりの時間を確保しにくい場合は、行きたかった場所に出かけたり、自然の多い場所でのんびり過ごしたりするのも効果的です。もっとも大切絵なことは、ストレス源となる問題を思い出さずに、ひとり時間をしっかりと楽しむこと。夢中になれる趣味や外出を取り入れれば、心がよりリラックスしやすくなりますよ。
まとめ
いかがでしたか。心の正体は脳の働き。だからこそ、脳に良い生活習慣を心がけることで、心の健康を保ちやすくなるという記事でした。読者の中には、「急に生を変えるのは難しい」と感じる人もいるかもしれません。ですが、あなたの脳や心は、日々の習慣の積み重ねで作られています。まずは、小さなことから始めてみてください。1〜3ヶ月続ければ、心の健康が整った実感を得られるはずですよ。
また、筆者のX(旧Twitter)では心の健康に関する情報を毎日発信しています。Instagramでは、実際に筆者が行なっている心の健康を保つための生活をご覧いただけます。さらに、noteでは心の健康に関する特別なコラムも公開していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
参考文献
安西祐一郎(2011). 心と脳――認知科学入門. 岩波新書.
岡市 廣成 & 鈴木 直人 監修 (2020). 心理学概論 第2版. ナカニシヤ出版.
樺沢 紫苑 (2020). 精神科医が教える ストレスフリー超大全――人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト. ダイヤモンド社.
熊野宏昭(2007). ストレスに負けない生活: 心・身体・脳のセルフケア. 筑摩書房
厚生労働省 こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (n.d.). 1 ストレスとは:ストレス軽減ノウハウ. https://kokoro.mhlw.go.jp/nowhow/nh001/
サトウ タツヤ & 高砂 美樹 (2022). 流れを読む心理学史〔補訂版〕: 世界と日本の心理学. 有斐閣アルマ
新R25 Media(2021). 「休日何もしてないのに、休めてない気がする」のはなぜ!? 茂木健一郎直伝“最強の休み方”. https://r25.jp/articles/928885231139684353
BATHCLIN(n.d.). 良い睡眠はお風呂から! 入浴で睡眠の質を変えよう. https://www.bathclin.co.jp/health-column/211126_13/
VOGUE JAPAN(2023). 朝食はいつ食べるのがベスト? 抜くとどうなる? 栄養士が気になるポイントを解説. https://www.vogue.co.jp/article/in-vogue-the-best-time-to-eat-breakfast
Cohen, S., Janicki-Deverts, D., & Miller, G. E. (2007). Psychological stress and disease. JAMA, 298(14), 1685-1687. https://doi.org/10.1001/jama.298.14.1685
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Springer Publishing Company.
American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). American Psychiatric Association.
